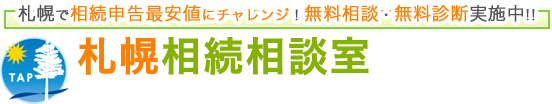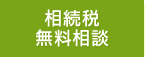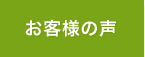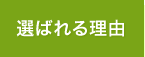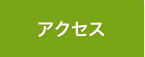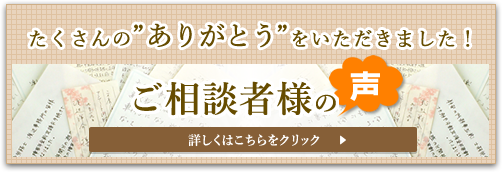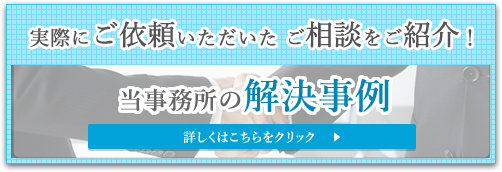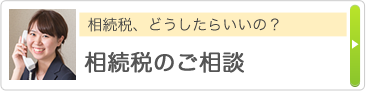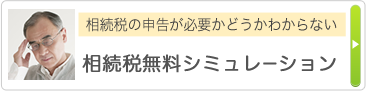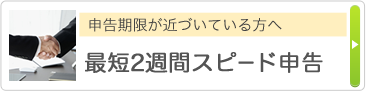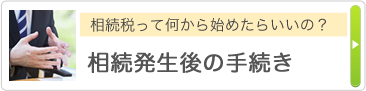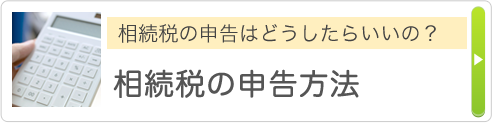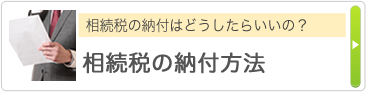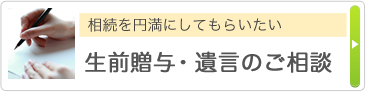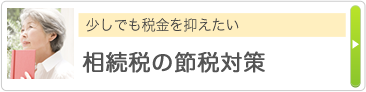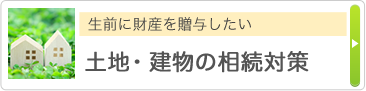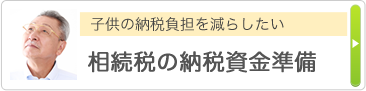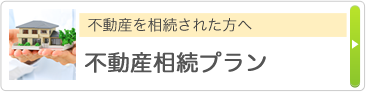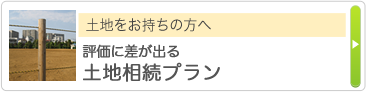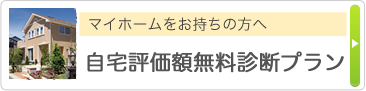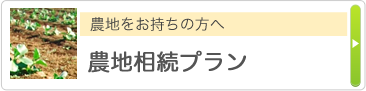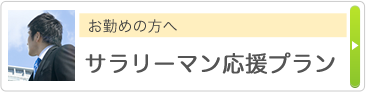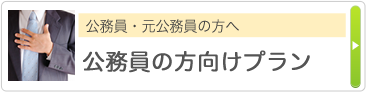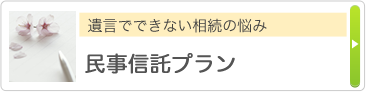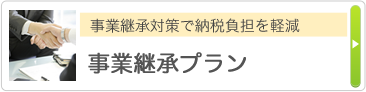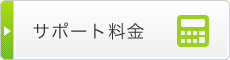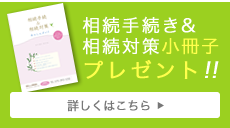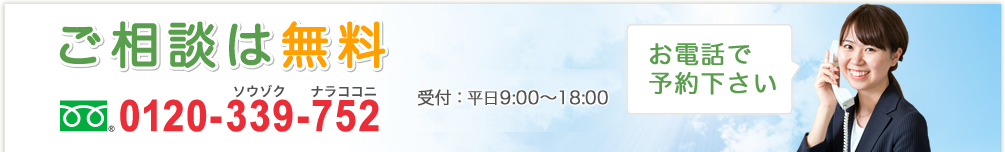負担のある遺贈(遺言による相続)を断りたいのですがどうすれば宜しいでしょうか?
基本的に遺言者の死後3か月以内でしたら遺贈を放棄することができます。
この3か月という期間はポイントとなります。現金・不動産などの単純遺贈であったり、「老後の面倒」などの負担付遺贈であったりしても同じです。
遺産の全部又は一定割合を遺贈する「包括遺贈」では3か月以内に家庭裁判所(相続開始地か遺言者の住所地)で放棄の申立てをする必要がありますが、具体的に財産を特定した「特定遺贈」の場合は遺言者の死後に相続人や遺言執行者に書面を送るなどの意思表示をすればいつでも放棄できます。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※小規模宅地等の特例
相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと50%又は80%の減額が認められる制度。
相続相談室(Q&A)の最新記事
- 夫の籍に入っていない事実婚の妻の相続はどうなりますか
- 親より先に子どもが亡くなっているときの相続はどうなりますか
- 亡くなった人の兄弟姉妹が相続出来るのはどういう場合ですか
- 亡くなった人の親が相続できるのはどういう場合ですか
- 遺言のない相続では妻(夫)と子はどのような割合で受け取れますか
- 遺言がない場合には誰が相続できるのでしょうか。
- 自筆証書遺言の作り方
- 遺言の方式と種類
- 所有権と受益権の相違点について教えてください。
- 受託者が受益権を有する場合
- 自己信託
- 破産管財人が信託財産を処分しようとするときは、受益者は破産管財人に対して処分をやめることを請求することができますか。
- 信託財産は、受託者の債権者から守られるのでしょうか。
- 信託の変更はどのように行えばよいのでしょうか。
- 信託契約の受益者の変更
- 民事信託と商事信託
- 遺言書の作成方法を教えてください。
- 信託した財産は誰のものになるのでしょうか。
- 信託とは具体的にどのようなことをいうのでしょうか。また信託における登場人物を教えてください。
- 信託を活用すると、具体的にどのようなことができるようになるのでしょうか。
- 成年後見人に対する報酬と相続債務
- 贈与税における土地の時価
- 海外財産について二重課税はあるのか
- 微妙な相続財産の範囲
- 未分割財産の譲渡
- 相続開始後の被相続人の債務の免除
- 死因贈与と遺留分減殺請求について
- 住宅取得等資金の贈与に関して、相続開始前3年以内の贈与について相続財産に加算しなければならないですが、非課税となった住宅取得等資金はどうなりますか
- 住宅取得等資金の贈与に関して、住宅ローンの返済にあてることは?
- 住宅取得等資金の贈与に関して複数の者からの贈与があったときの扱いはどうなりますか?
- 住宅取得等資金の贈与に関して、親から住宅を贈与されましたがこのような場合も非課税になりますか?
- 住宅取得等資金の贈与に関して、配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合は非課税の扱いにできるでしょうか?
- 教育資金の一括贈与について、金融機関に拠出する際に複数回に分けられますか?
- 教育資金の一括贈与について、実施の際に具体的に手続きはどのように行えばよいですか?
- 教育資金の一括贈与について、学校の制服や体操服、上履き、通学かばんなどを業者に支払った場合はどうですか?
- 教育資金の一括贈与について、下宿代は非課税の対象になりますか?
- 教育資金の一括贈与について、対象となる「学校等」と「学校等以外の者」とは具体的にどのようなものですか?
- 結婚・子育て資金の一括贈与について、祖父母からそれぞれ贈与を受けましたが、契約の終了前に祖母の方が死亡しました。この場合の残高の扱いはどうなりますか?
- 結婚・子育て資金の一括贈与について、使う契約の終了前に贈与者が死亡しました。この場合の取扱いはどうなりますか?
- 結婚・子育て資金の一括贈与について、教育資金の一括贈与の特例と合わせて受けることはできますか?
- 結婚・子育て資金の一括贈与について、未婚でもこの制度を利用できますか?
- 亡くなった人が営んでいた店舗を、相続中の申告期限前に別の業種に転業した場合も小規模宅地等の特例は使えますか?
- 複数の宅地を居住用にしていたとき、小規模宅地の特例はどうなりますか?
- 亡くなった人は建物の一部を居住用とし、残りを賃貸用としていましたが、小規模宅地等の特例は使えますか?
- 相続人が亡くなった後に複数の遺言が出てきた場合どれが有効となりますでしょうか?
- 一度作成した遺言は取り消すことは出来ますでしょうか?
解決事例
-
- 2026.01.28
- あとから贈与が発覚したケース
-
- 2025.12.19
- 税理士法33条の2(書面添付)を活用したケース
-
- 2025.11.27
- 過去の相続財産が混在するケース