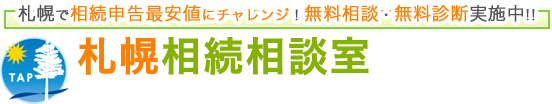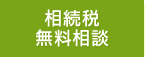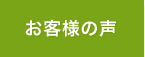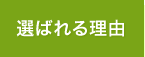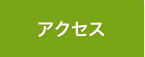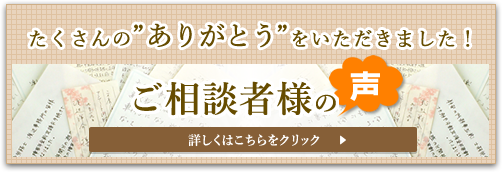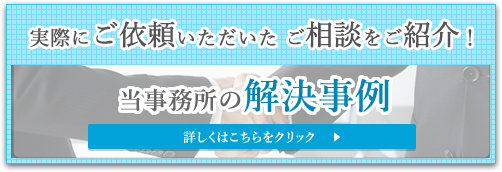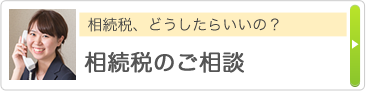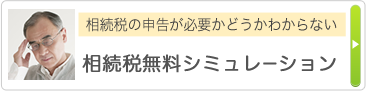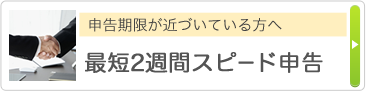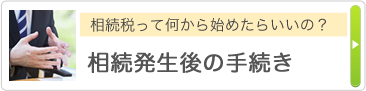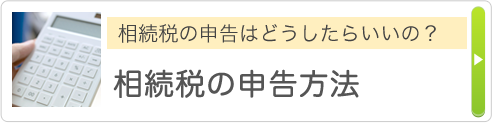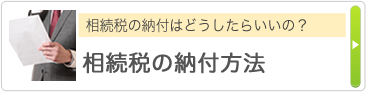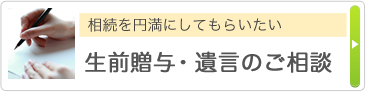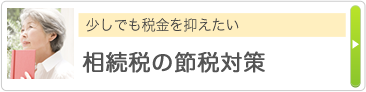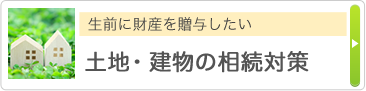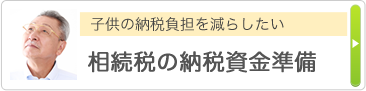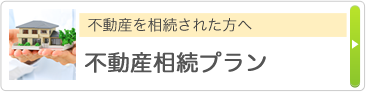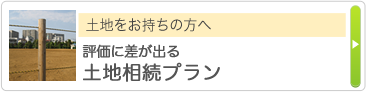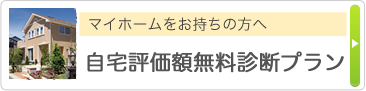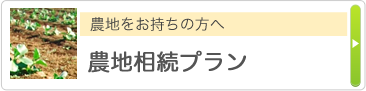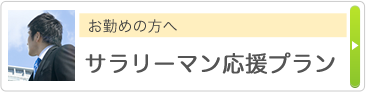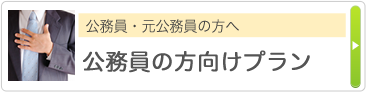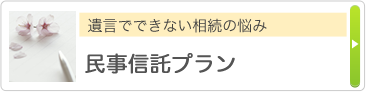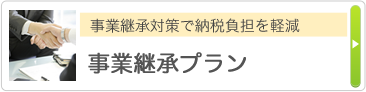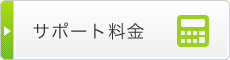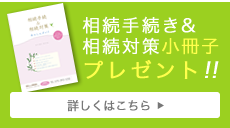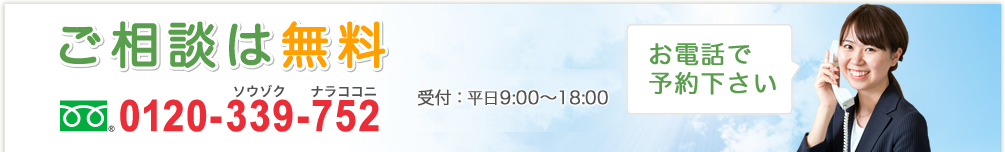新着情報
遺言がない場合には誰が相続できるのでしょうか。
A.民法の決めた相続順位にしたがって相続人が決まります。
法定相続では、子供が最優先の相続人となり、他に相続出来るのは配偶者(妻・夫)となります。
親が相続出来るのは亡くなった人に子供がいないとき、また兄弟姉妹が相続できるのは亡くなった人に子供も親もいないときです。
(上記は更新日時点での内容となります。)
続きを読む >>
公正証書遺言作成までの手順
実際に公正証書遺言を作成する際には、公証人に当日口述して、その場で完成させるわけではなく、あらかじめ遺産のリスト・不動産登記簿謄本・戸籍謄本等と遺言の草案を、事前に郵送等で公証人に届けておきます。
その後、打ち合わせを行い、内容を固めておきます。
そして、当日は、公証人が作成しておいた遺言書を遺言者に読み聞かせ、意思確認の後に署名押印するのが一般的です。 具体的な流れは次の通りです。
続きを読む >>
公正証書遺言の作成時の証人
公正証書遺言を作成する場合、証人2人の立会いが必要です。
親しい友人がいればその人にお願いすることも可能ですが、財産内容や家庭内の事情を知られることはあまり好ましくありません。そのため、守秘義務のある専門家に依頼するのが望ましいでしょう。遺言書作成時に財産内容や相続税のことを相談した税理士、弁護士、行政書士等の専門家をお薦めします。
なお、以下の人は証人にはなれません。
① 法定相続人
続きを読む >>
公正証書遺言のメリット・デメリット
<メリット>
① 遺言者は、口述するだけでいい
② 公証人という専門家が作成してくれる
③ 遺言の保管が確実であるため、紛失、変造の心配がない
④ 家庭裁判所の検認の必要がない
<デメリット>
① 証人2人の立会いがいる
② 手続きが面倒であり、公証人の手数料がかかる
③ 遺言の存在と内容がオープンになる
●公証人とは?
法
続きを読む >>
公正証書遺言の基礎知識
公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、その口述した内容をもとに公証人が作成する遺言です。
公正証書遺言は、全国各地の公証役場で作成されます。また、遺言者が高齢者である、病気等の理由で公証役場に行くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅または病院等へ出張して遺言書を作成することも可能です。
作成された遺言書の原本は公証役場で保管されるため、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざ
続きを読む >>
自筆証書遺言の作り方 ステップ4
<開封時には必ず家庭裁判所で検認を受ける>
相続人が家庭裁判所に出向き、遺言書を提出します。この際、相続人は被相続人との身分関係等を明らかにするためにも、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本・住民票を持参します。また、遺言が被相続人の自筆であることを明らかにするためにも、被相続人の直筆の書類も持参します。
家庭裁判所の検認を受けるまでの期間は、提出してから通常1~2ヵ月程度かかる
続きを読む >>
自筆証書遺言の作り方 ステップ3
<遺言書を保管する>
せっかく作成した遺言書も、死後に発見されなければ意味がありません。したがって、遺族が見つけやすいところに保管しておきます。ただ、生前には遺言の内容を家族に知られたくない場合もあります。このような場合は、金融機関の貸金庫や信頼できる友人等に保管を依頼しておきます。ただし、金融機関の貸金庫を遺族が開けるのは事務的な手間がかかりますので、生前に配偶者等自分
続きを読む >>
自筆証書遺言の作り方 ステップ2
< 清書 >
① 遺言書のすべてを遺言者の自筆、すなわち手書きで行う
「遺言書」というタイトル、遺言の内容である本文、本文の最後や封筒の日付及び署名等すべてを被相続人の手書きで行います。代筆やパソコンでの作成による遺言は無効です。縦書きでも横書きでもかまいません。また、万年筆、ボールペン、筆等、書く物は何でもかまいませんが、変造される危険性が高いため、鉛筆を使用することは避けます。
②
続きを読む >>
自筆証書遺言の作り方 ステップ1
<事前準備>
① 法定相続人及び法定相続分の確認
法律上、誰が相続人(法定相続人)か、それぞれの相続人はどのくらい財産をもらう権利があるのか(法定相続分)を確認します。
② 財産の一覧表の作成
誰に何を相続させるのかを決定しやすくするためにも、自分にどれだけの財産があるのかを把握します。この場合、現預金、不動産、株式等プラスの財産だけでなく、借金等マイナスの財産も忘れないように一
続きを読む >>
自筆証書遺言の作り方
Q. 自筆証書遺言とは?
A. 自筆証書遺言には、「いつでもどこでも作成できる」「証人を必要とせず、1人でできる」「特別な費用がかからない」といったメリットがある半面、「様式や内容の不備が生じやすい」「相続開始時に家庭裁判所の検認を受けなければならない」「偽造、変造、紛失の可能性がある」といったデメリットがあり、選択にあたっては、これらの点を検討する必要があります。
財産の額が高額でない人
続きを読む >>
解決事例
-
- 2025.10.30
- トラブルになりかけていても相続税ゼロで申告を終えられたケース
-
- 2025.09.19
- 想定よりも相続税額を抑えられたケース
-
- 2025.08.27
- 相続財産の中に投資信託が多く含まれるケース