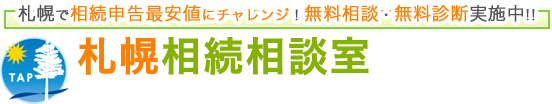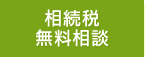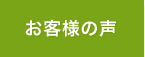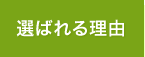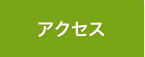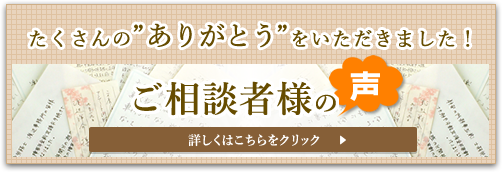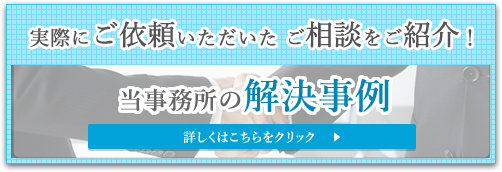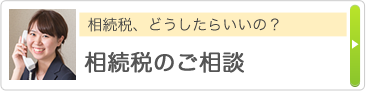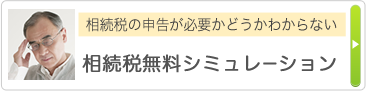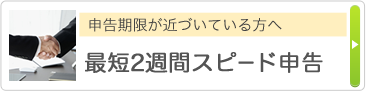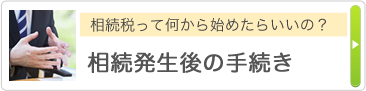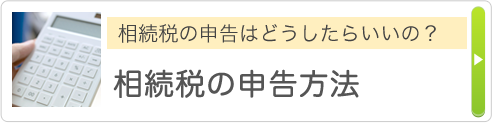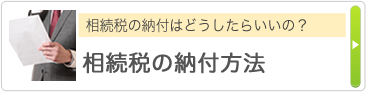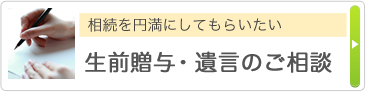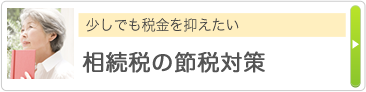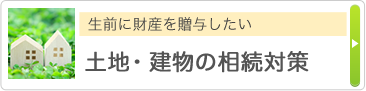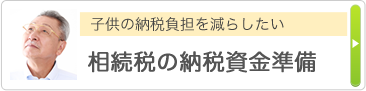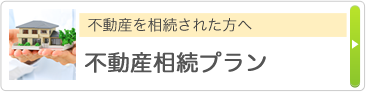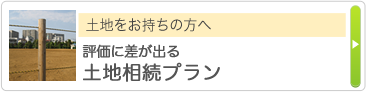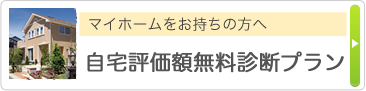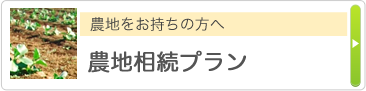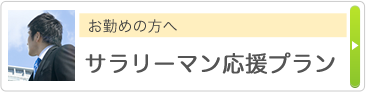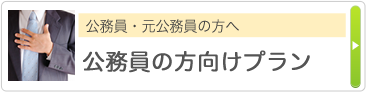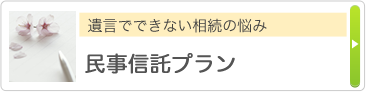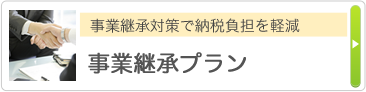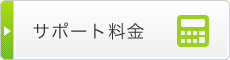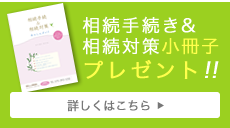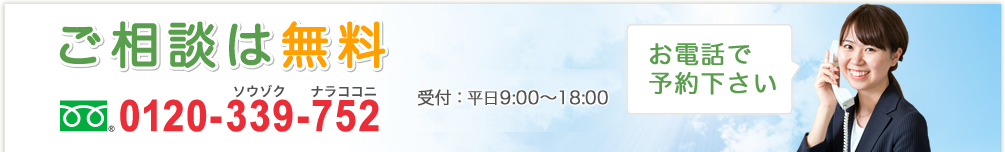相続情報室(コラム)
「家族信託その④ 信託財産(信託受益権)の評価」(No.60)
信託財産における資産負債は、財産評価基本通達に定める方法により評価した課税時期における財産価額によって評価します。
受益者が生存中に受益権を贈与した場合はもちろんのこと、信託契約により受益者が変更されるなど、適正対価がないまま、受益権が前の受益者から異動した場合には、贈与により取得したものとみなされ(みなし贈与)、受益権取得時の信託受益権の評価額をもとに贈与税が課されます。
&n
続きを読む >>
「家族信託その③ 信託終了時の贈与税・相続税」(No.59)
家族信託が終了したときは、受益者から帰属権利者に信託財産が移動する場合、当該信託の信託財産の相続税評価額が50万円以下である場合を除き、信託契約の日の属する月の翌月末日までに「信託に関する受益者別調書」「信託に関する受益者別調書合計表」を所轄の税務署に提出することになります。
受益者と帰属権利者を別の人を設定しているときには、残余財産取得に対する適正な対価の授受がない場合には、贈与
続きを読む >>
「家族信託その② 信託期間中の税務手続き」(No.58)
家族信託を行っている期間での税務はどのように行われるのでしょうか。
まず税務上、信託の受益者が当該信託の資産負債が属するとみなし、信託財産に帰属する収益物件からの家賃・利息などの収益と費用は受益者に帰属し、受益者の所得となることから受益者が毎年確定申告をすることとなります。
また信託会社以外の受託者は「信託の計算書」「信託の計算書合計表」を毎年1月31日までに税務署へ提出する必要が
続きを読む >>
「家族信託その① 家族信託とは」(No.57)
家族信託とは何なのか、
それは一言でいうならば
「認知症になった人の財産管理を家族に任せるため民事信託契約」です。
もちろん認知症になることに備えて事前に契約を結ぶことも含みます。
メリットとしては、
①認知症になった時の財産管理の不安を軽減できる
②遺言書のような厳格な文章にしばられることなく、契約で人に任せることができる。
③二次相続について指定ができる。
続きを読む >>
「仮想通貨と相続」(No.56)
仮想通貨(ビットコイン他)を相続する場合は、税金についてどのように考えれば良いのでしょうか。
まずは被相続人が閲覧していたサイトから、亡くなられた日と今現在の運用残高を見てみます。
仮想通貨はウォレット(仮想世界上の財布)というものに保管されておりますが、そのIDやパスワードがあれば閲覧サイトの中身を見ることができます。
そして相続発生日、すなわち被相続人が亡くなられた日
続きを読む >>
みなし相続財産とは
被相続人の死亡によって受け取る生命保険金は被相続人が所有していた財産ではないので、本来は相続財産ではありません。しかし、このような財産も本来の相続財産を取得するのと同等の価値があるため相続税では相続や遺贈によって取得した財産とみなして課税することにしています。
このようなものを「みなし相続」といい、おもに次のものがあります。
生命保険金・損害保険金
被相続人の死亡によって受け取る生命保険金や
続きを読む >>
相続税対策には(5)
1 節税対策
2 納税資金対策
の大きく2つの考え方があります。
以下に有効な対策の一つをご紹介します
相続人を増やし、税率を下げる
相続税を減らすには、相続人の数を増やすという方法が有効です。
相続人を増やすと一人当たりの相続額が減り、税率区分を下げることができます。
相続人が1人増えるごとに基礎控除額が600万円追加されます。
(そのために有効なのが
続きを読む >>
相続税対策には(4)
1 節税対策
2 納税資金対策
の大きく2つの考え方があります。
以下に有効な対策の一つをご紹介します
「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例」の活用
非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例
後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合に
続きを読む >>
相続税対策には(3)
1 節税対策
2 納税資金対策
の大きく2つの考え方があります。
以下に有効な対策の一つをご紹介します
納税資金として生命保険を活用
納税資金にあてる目的で大口の生命保険に加入すると、保険金でスムーズに現金を用意することができます。また、保険の掛け金を払うことで、相続財産を減らすことができ、かつ、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用することができます
続きを読む >>
相続税対策には(2)
1 節税対策
2 納税資金対策
の大きく2つの考え方があります。
以下に有効な対策の一つをご紹介します
生前贈与の活用
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、自宅や自宅の購入資金を贈与する場合には、一定の条件を満たせば、基礎控除額(110万円)のほかに2,000万円の非課税枠が加算されます。
住宅取得等資金の贈与
続きを読む >>
解決事例
-
- 2026.01.28
- あとから贈与が発覚したケース
-
- 2025.12.19
- 税理士法33条の2(書面添付)を活用したケース
-
- 2025.11.27
- 過去の相続財産が混在するケース