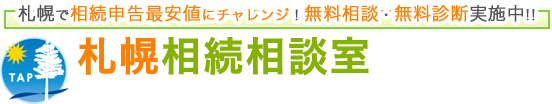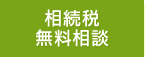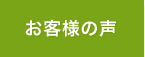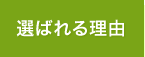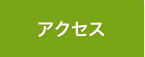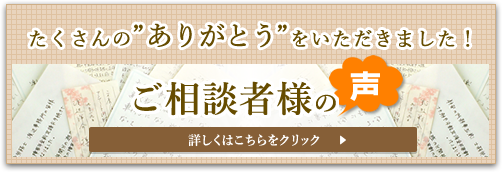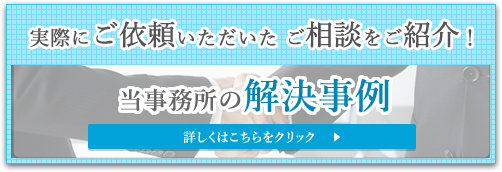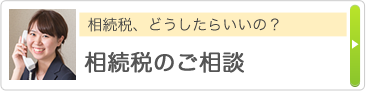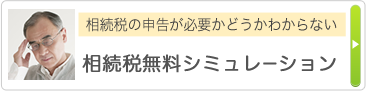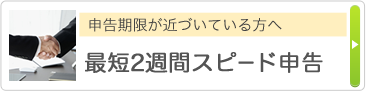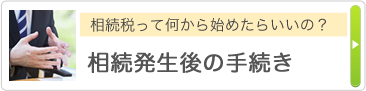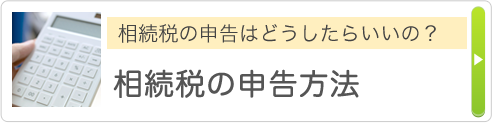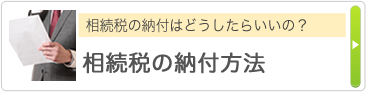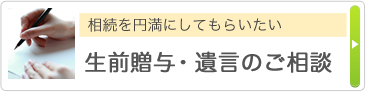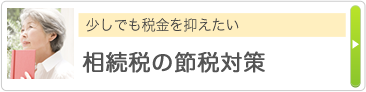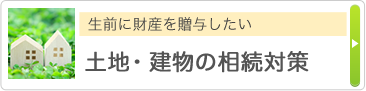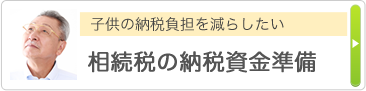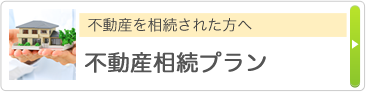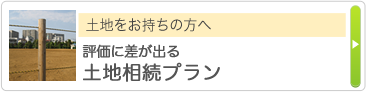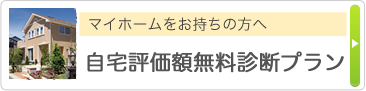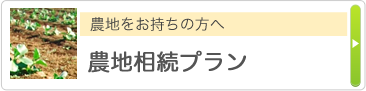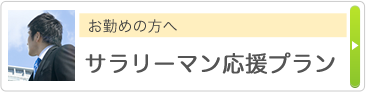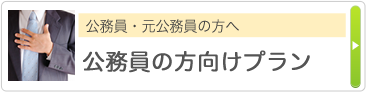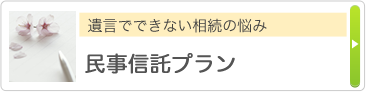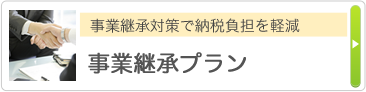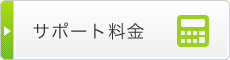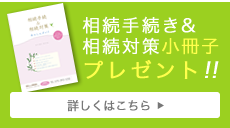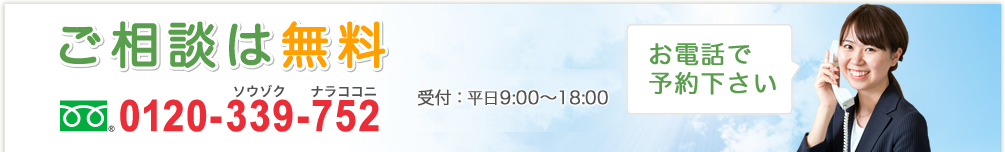新着情報
遺言書の保管と執行の方法
遺言書の保管
遺言書は発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の法的効力も持ちません。従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人がすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
遺言の保管方法
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。従って、相続人等に遺言書を作
続きを読む >>
土地の有効活用による相続税対策(土地の利用区分変更)
都心や市街地にある土地の評価額は路線価をベースに決められますが、2つ以上の道路に面している土地は評価が高くなります。また、その価額は、土地が接している道路のうちでもっとも高い路線価(正面路線価といいます)をもとに決められます。
そこで、比較的広い土地が複数の道路に面しているときは、土地の利用区分を変更・分割することによって、土地の評価額を下げることができます。とくに、一方が幹線道路など路線価
続きを読む >>
マイホームの贈与方法
結婚20年以上の夫婦の場合贈与税の配偶者控除を活用できます。
この制度は婚姻期間が20年以上の配偶者へ居住用不動産、または居住用不動産を取得するための資金を贈与する場合には、最高2000万円を課税価格から控除できるというものです。基礎控除と合わせると2110万円まで無税で贈与することができることになります。
この特例を利用した贈与は、相続前3年以内に行ったものでも相続財産に取り込まれること
続きを読む >>
孫に贈与する方法
「一代飛び越し贈与」子を飛び越して贈与すれば、今回の相続だけでなく、子の相続時の財産も同時に減らすことができます。そして、その贈与財産については、相続税の課税を1回免れることになるわけです。
連年贈与を10年行ったところで被相続人が死亡すれば、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算するというルールがあるため、3年分の贈与が無駄になってしまいますが、孫などの相続人でない人に対する贈与は相続
続きを読む >>
生命保険の活用(被保険者の活用方法)
父親を被保険者とする生命保険に加入しようと思っても年齢や健康上の理由などから加入できないケースもあります。こんなときは母親を被保険者とするのもひとつの方法です。契約者と受取人は子とします。
このような保険加入にはどんな効果があるかといいますと
まず、父親が先に死亡した場合、保険金は支払われませんが、母の二次相続時には保険金が支払われますので、それを納税資金などに利用することができます。
続きを読む >>
収益物件は所得の低い子などが取得する
賃貸マンションなどの収益物件は子が相続すると有利ですが、さらに相続後の税負担を考えあわせると、所得の低い人が取得するのがもっとも有利となります。
相続後の収益は所得税の対象になりますが、所得税は超過累進税率であるため、所得が高い人であれば負担が重くなります。
相続税のことだけでなく所得税や他の税金の観点からも考えることが大切です。
例えば不動産を相続したはいいが固定資産税が負担で苦しむ形
続きを読む >>
課税対象者が増えた相続税の課税割合一覧
平成27年1月以降の相続から相続税の基礎控除が以前の60%にまで引き下げられて、相続税の課税対象者が大幅に増加しました。この現象の全国的な数字を分析してみたいと思います。
課税割合
27年分の相続で被相続人(亡くなった人)全体に占める課税された者の割合を27年分の課税割合といいます。この課税割合は26年分では4.4%であったものが、8%にまで急上昇しました。当初の財務省試算
続きを読む >>
お嫁さんのみに遺産を渡す場合
お世話になったお嫁さんのみに相続させるには養子縁組が必要です。
弊社の顧問先様でも社長の奥様が会長さんのお世話を献身的にしてあげている事例があります。
長年、献身的に世話をしてくれた嫁に遺産をあげたいと思っても、お嫁さんには相続権がありません。
お嫁さんに財産を与える方法としては、1.養子縁組、2.遺贈、3.生前贈与の3つが考えられます。
1.養子縁組をしますと、お嫁さんにも子として
続きを読む >>
土地の分割取得で評価額を下げる方法
土地を複数の相続人で分割して取得しますと、分割後の利用区分ごとの評価となり、相続税が安くなることがあります。
たとえばですが、2つ以上の道路に接している土地はひとりの相続人が取得(または複数の相続人が共有)するより、分割して取得するほうが二方路線の加算がなくなったこと、また、一方の土地が路線価の高い道路から切り離されたことにより、評価額が大幅に下がります。
こちらは相続発生後に分筆の登記
続きを読む >>
家業を承継する長男だけに財産を引き継ぐための遺言
家業を承継する長男に事業資産を集中させる場合、兄弟間の遺産分割協議が焦点になります。
民法では、きょうだいは均等に相続することになっていますが、事業用財産を分割してしまうと経営が成り立たなくなるという問題があります。
そこで、後継者である長男に事業用財産をすべて相続させる意図の遺言書が必須となります。しかし、他のきょうだいには遺留分がありますので、これだけでは不十分です。遺留分相当の財産が
続きを読む >>
解決事例
-
- 2025.12.19
- 税理士法33条の2(書面添付)を活用したケース
-
- 2025.11.27
- 過去の相続財産が混在するケース
-
- 2025.10.30
- トラブルになりかけていても相続税ゼロで申告を終えられたケース