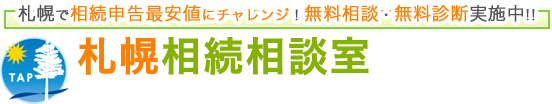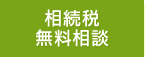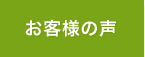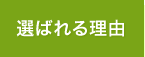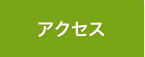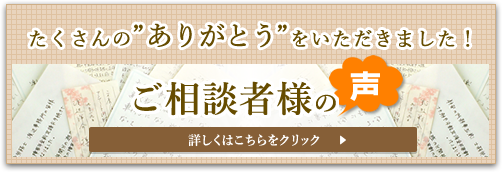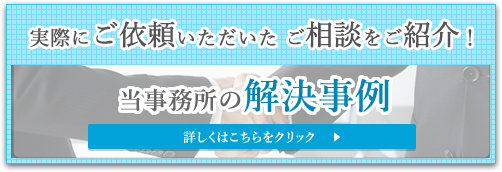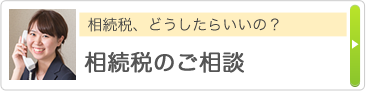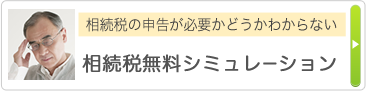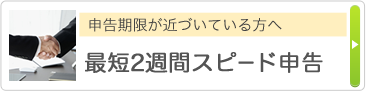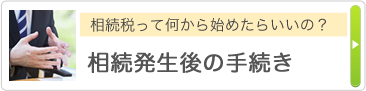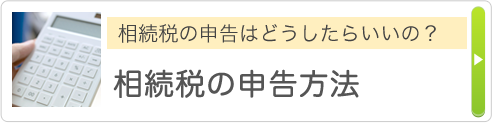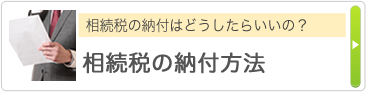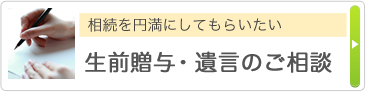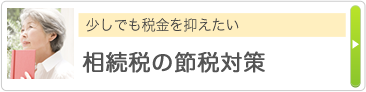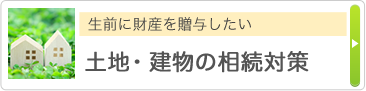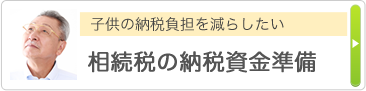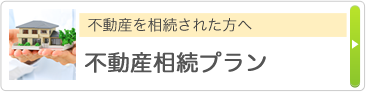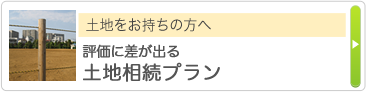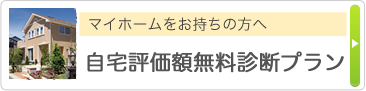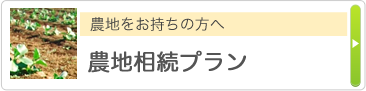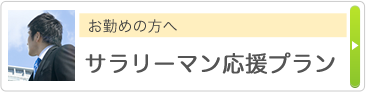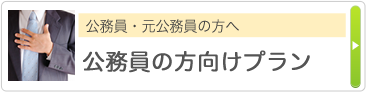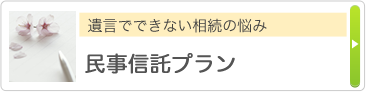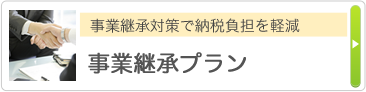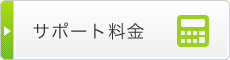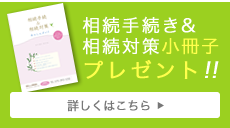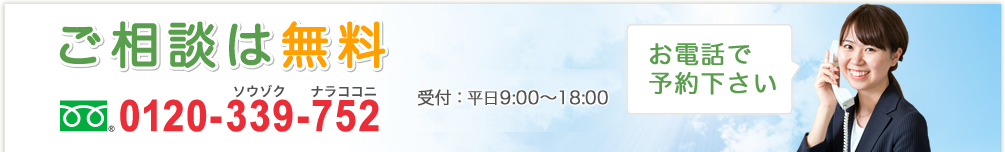新着情報
相続税対策には(5)
1 節税対策
2 納税資金対策
の大きく2つの考え方があります。
以下に有効な対策の一つをご紹介します
相続人を増やし、税率を下げる
相続税を減らすには、相続人の数を増やすという方法が有効です。
相続人を増やすと一人当たりの相続額が減り、税率区分を下げることができます。
相続人が1人増えるごとに基礎控除額が600万円追加されます。
(そのために有効なのが
続きを読む >>
相続税対策には(4)
1 節税対策
2 納税資金対策
の大きく2つの考え方があります。
以下に有効な対策の一つをご紹介します
「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例」の活用
非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例
後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合に
続きを読む >>
相続税対策には(3)
1 節税対策
2 納税資金対策
の大きく2つの考え方があります。
以下に有効な対策の一つをご紹介します
納税資金として生命保険を活用
納税資金にあてる目的で大口の生命保険に加入すると、保険金でスムーズに現金を用意することができます。また、保険の掛け金を払うことで、相続財産を減らすことができ、かつ、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用することができます
続きを読む >>
相続税対策には(2)
1 節税対策
2 納税資金対策
の大きく2つの考え方があります。
以下に有効な対策の一つをご紹介します
生前贈与の活用
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、自宅や自宅の購入資金を贈与する場合には、一定の条件を満たせば、基礎控除額(110万円)のほかに2,000万円の非課税枠が加算されます。
住宅取得等資金の贈与
続きを読む >>
相続税対策には
節税対策
納税資金対策
の大きく2つの考え方があります。
以下に有効な対策の一つをご紹介します。
対策 所有財産の評価を下げる
土地や建物は、利用状況に応じて財産評価基本通達により評価減がありますので、下記のような方法で土地・建物の評価を下げる可能です。
更地で土地を持っている場合は、一定の要件を満たす建物を建てることで相続税評価額を大きく下げることができます。(何も建てていない更地の
続きを読む >>
土地の有効活用による相続税対策(貸家建築)
地主の相続税対策として、よく土地の有効活用ということがいわれ、代表的な方法が遊休地あるいは自宅敷地の余裕部分にアパートやマンションなどの貸家を建てる方法で、いまや相続税対策の常套手段ともなっています。
たしかに不動産経営の採算がとれるのであれば、この方法は非常に効果的です。
その効果は以下の4つです。
1 小規模宅地の特例が使える
空き地などに貸家を建てると、その土地は事業用宅地(貸付用
続きを読む >>
相続税の掛かる贈与財産
被相続人から生前贈与を受けた財産のうち次のものは、相続財産に取り込んで相続税が課税されることになっています。
相続時精算課税制度に係る贈与財産
被相続人から贈与を受けた際に相続時精算課税制度を選択した子がいる場合、その子が本制度の適用以後に被相続人からもらったすべての財産が相続税の課税対象となります。
相続開始前3年以内の贈与財産
相続や遺贈によって財産
続きを読む >>
相続時精算課税制度の活用(収益物件への利用)
収益物件の贈与は効果的です。
賃貸物件は時価より安く贈与できます
建物の相続税評価額は固定資産税評価額で評価されます。それは建築費用の約60%です。さらに賃貸となれば借家権(通常30%)が控除されるので、おおまかに言えば、時価の約42%で評価されるのです。相続時精算課税を使えば、時価6000万円弱の賃貸物件なら評価額は約2500万円。
したがって2500万円の特別控除によ
続きを読む >>
土地の売却方法
相続税の納税のために、相続した土地や建物を売却することがあり、このとき譲渡所得税と住民税がかかりますが、いくつかのポイントを押さえておくと税負担を軽くすることができます。
① 所得税の納税資金を残しておく
売却した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるものは長期譲渡、5年以下は短期譲渡に区別され、長期の場合は所得税・住民税あわせて20%の税率ですが、短期は原則として売却益の39%もの税金が
続きを読む >>
相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度をいったん選択すると、相続時までの継続適用となり、途中で変更することができなくなります
暦年課税の基礎控除(年額110万円)が使えなくなります
生前贈与をしても直接的な相続財産の減少にはならなくなります・(相続時に相続財産に加算)
相続時精算課税制度を選択した親や祖父母からの贈与については少額の贈与であってもすべて申告が必要になります。
小規模宅地等の特例が使
続きを読む >>
解決事例
-
- 2025.12.19
- 税理士法33条の2(書面添付)を活用したケース
-
- 2025.11.27
- 過去の相続財産が混在するケース
-
- 2025.10.30
- トラブルになりかけていても相続税ゼロで申告を終えられたケース