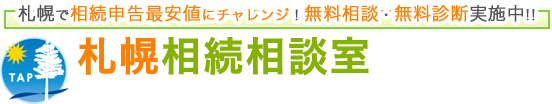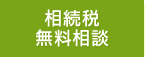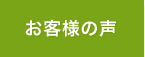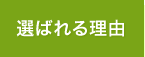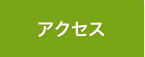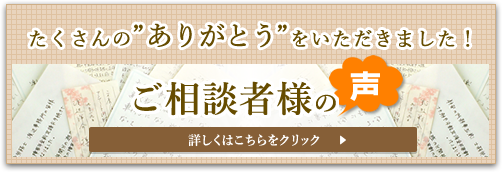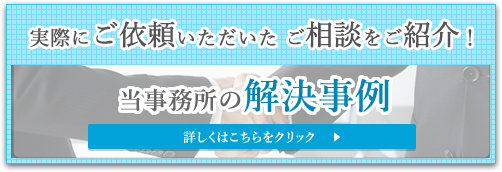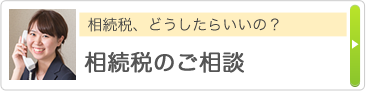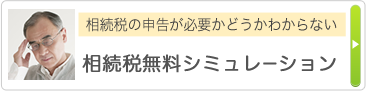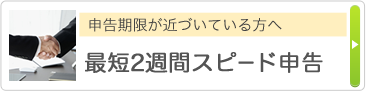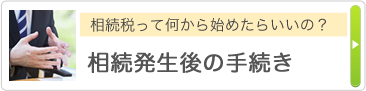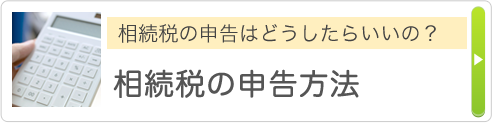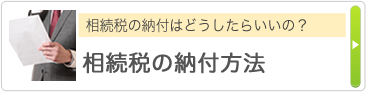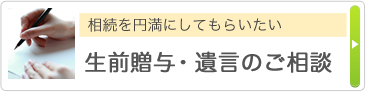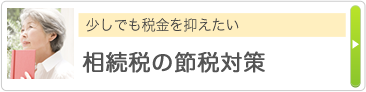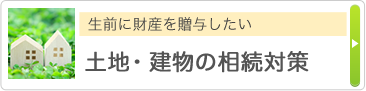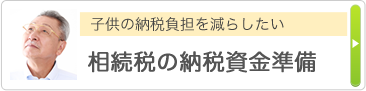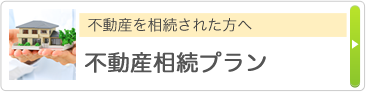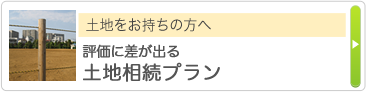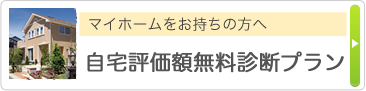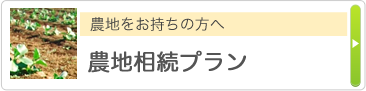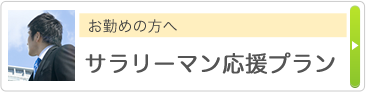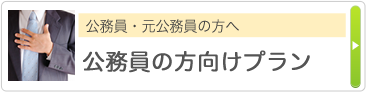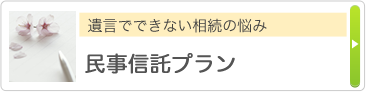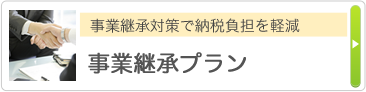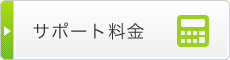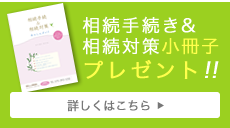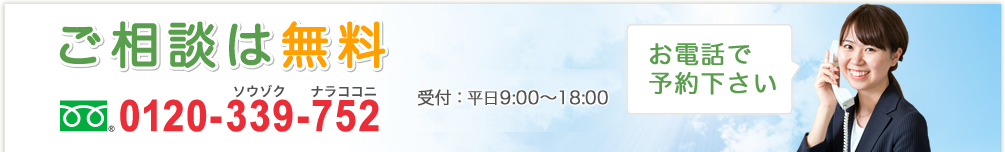相続情報室(コラム)
非課税財産
相続税のかからない財産の例には次のものがあります。
・墓地・仏壇ほか
墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚などは日常礼拝の対象とされていることから非課税となります。
・相続人が取得した保険金のうち一定額
相続によって取得したとみなされる生命保険金や損害保険金のうち「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。
・相続人が取得した死亡退職金のうち一定額
相続によって取得したとみなされ
続きを読む >>
配偶者の税額軽減
遺産額がそれほど大きくなく、二次相続時の税負担が生じない場合は、配偶者の税額軽減をフルに使えるように遺産を分割するのが相続税面では有利です。
しかし、二次相続でも相続税が発生する場合は注意が必要です。二次相続では当然配偶者がいなくなっているため配偶者の税額軽減は使えません。一次相続の配偶者の取得分を大きくしすぎると、子どもの税負担が予想以上に重くなることがあります
配偶者と子どもの取得割合
続きを読む >>
収益物件は子どもが相続する
賃貸マンションやアパートなど高い収益を生む財産は、
できれば子どもが相続するほうがよいでしょう。
なぜなら、こういった収益物件を配偶者が取得してしまいますと、
二次相続時の財産がふくれあがってしまうからです。
同様に、株式や土地などのうち将来値上がりする可能性のある財産も、
なるべく子どもが取得するというのが相続税対策の基本的な考え方です。
相続でなく贈与をしてしまいたいときはもちろん
続きを読む >>
相続税対策の2つの方法
相続税対策には
①節税対策
②納税資金対策
があります。
まず、節税のための手法としては、おもに次の3つがあります。
①相続財産を減らす……相続人などに財産を移転(贈与)する
②相続財産の評価を下げる……たとえば自用地を貸家建付地にするなど、財産を評価の低いものに変える
③税法の計算規定を利用する……生命保険金の非課税枠、養子縁組など、税法の計算規定を利用
続きを読む >>
相続相談会を実施しました
2017年12月16日と17日、年の瀬も迫る頃に
イオン札幌琴似店にて相続の無料相談会を実施させて頂きました。
実際に相続が起こった後の資産管理のご相談、親子間の土地の使用貸借のご相談、遠方実家の売却のご相談、などなど。
「110万円の基礎控除を超えると絶対ダメなの?」というご質問も頂きましたので、相続時精算課税制度や住宅取得等資金の贈与などについてもお話させて頂きました
続きを読む >>
解決事例
-
- 2026.01.28
- あとから贈与が発覚したケース
-
- 2025.12.19
- 税理士法33条の2(書面添付)を活用したケース
-
- 2025.11.27
- 過去の相続財産が混在するケース