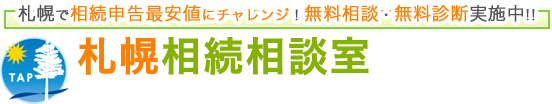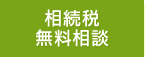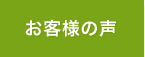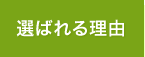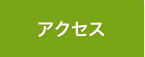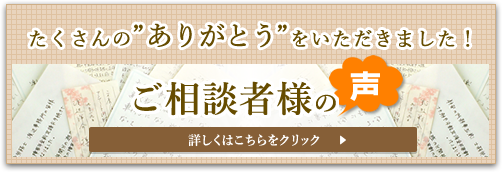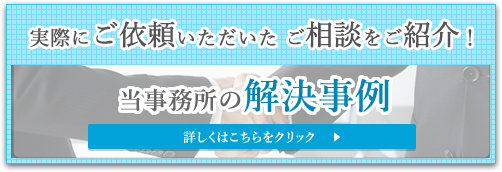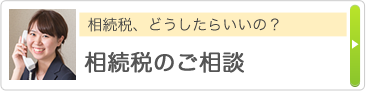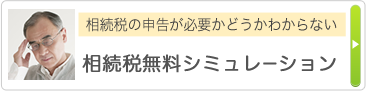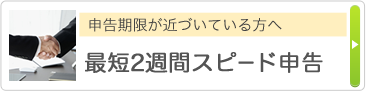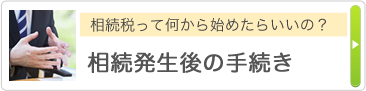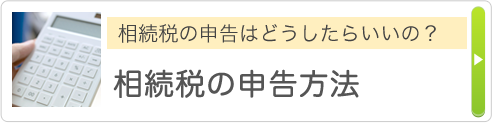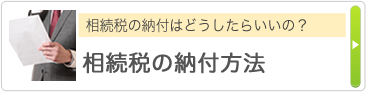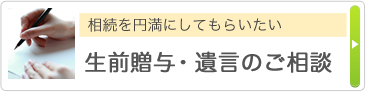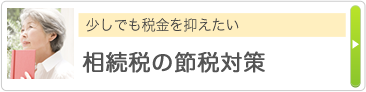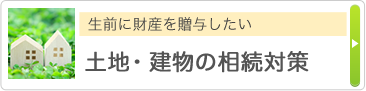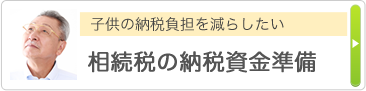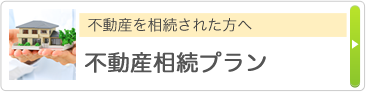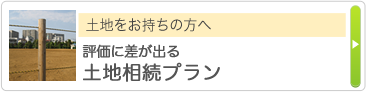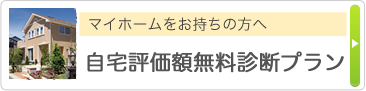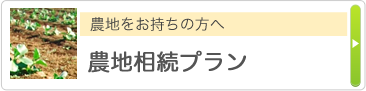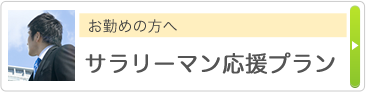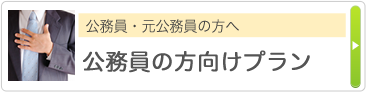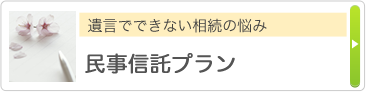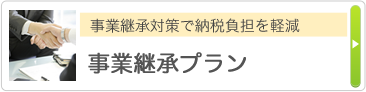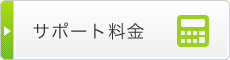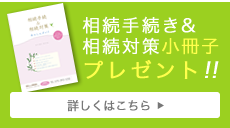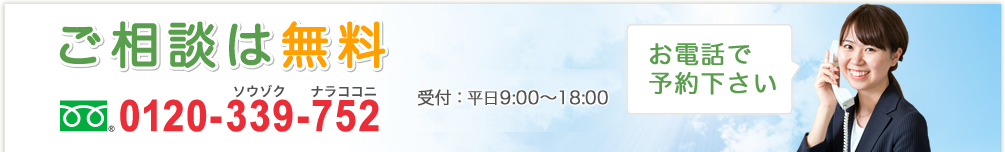新着情報
収益物件は子どもが相続する
賃貸マンションやアパートなど高い収益を生む財産は、
できれば子どもが相続するほうがよいでしょう。
なぜなら、こういった収益物件を配偶者が取得してしまいますと、
二次相続時の財産がふくれあがってしまうからです。
同様に、株式や土地などのうち将来値上がりする可能性のある財産も、
なるべく子どもが取得するというのが相続税対策の基本的な考え方です。
相続でなく贈与をしてしまいたいときはもちろん
続きを読む >>
微妙な相続財産の範囲
Q 今日は微妙な事案で悩んでいまして、ご相談に伺いました。
A そうですか?お悩みは早く解決したほうがよいですね。どうぞ、どうぞ。
Q 実はテナントさんが暫く外国出張するもので家賃をまとめて先払いされました。
その前受け賃料を今回の父の相続財産の相続税の計算上、債務控除出来るのでしょうか?
A 成程、若干微妙ですが、相続税法で債務控除に関する計算の規定が第13条及び14条にあります。
被
続きを読む >>
相続税対策の2つの方法
相続税対策には
①節税対策
②納税資金対策
があります。
まず、節税のための手法としては、おもに次の3つがあります。
①相続財産を減らす……相続人などに財産を移転(贈与)する
②相続財産の評価を下げる……たとえば自用地を貸家建付地にするなど、財産を評価の低いものに変える
③税法の計算規定を利用する……生命保険金の非課税枠、養子縁組など、税法の計算規定を利用
続きを読む >>
未分割財産の譲渡
Q そろそろ入梅の季節ですが、いつぞやは大変お世話になりました。今日は友人の乙氏から相続関係の相談にあたり、計算方法等をご教示いただきたく参上いたしました。
A 暫くです。あなたもお元気そうで何よりです。
Q 実は相続が完結していない状態で、相続財産のうち不動産を一部譲渡したという問題です。
A 成程、すっきり分割が纏まらないうちに、金銭の事情で土地を売却しなければならなくなったということで
続きを読む >>
相続相談会を実施しました
2017年12月16日と17日、年の瀬も迫る頃に
イオン札幌琴似店にて相続の無料相談会を実施させて頂きました。
実際に相続が起こった後の資産管理のご相談、親子間の土地の使用貸借のご相談、遠方実家の売却のご相談、などなど。
「110万円の基礎控除を超えると絶対ダメなの?」というご質問も頂きましたので、相続時精算課税制度や住宅取得等資金の贈与などについてもお話させて頂きました
続きを読む >>
相続開始後の被相続人の債務の免除
相続開始後の被相続人の債務の免除
Q 知人の会社のことで相談を受けました。その会社は同族会社です。実はその会社乙の元役員甲が会社から3千万円の借入をしていたのですが、甲が死亡したとき、取締役会が開かれ、結局その貸付金は全額免除するという決議がなされました。
甲の相続人から詳しいことは聞いていませんが、この場合、どのような税務関係や計算があるのか、お聞きしたくて参りました。
A それは大変ご
続きを読む >>
死因贈与と遺留分減殺請求について
Q こんにちは。早いものでもう12月です。ところで、ご相談なんですが、友人甲さんは亡くなられた父君から遺産約9億円のうち77%強の7億円を頂く死因贈与契約を結んでいました。他にも兄弟乙、丙がいるのですが、その税務問題について本日伺いました。死因贈与契約により取得した不動産については移転登記が終了しています。
A 父君と甲さんとの過ごしてきた生活環境や特に老後の介護関係等から父君の気持ちが甲さ
続きを読む >>
住宅取得等資金の贈与に関して、相続開始前3年以内の贈与について相続財産に加算しなければならないですが、非課税となった住宅取得等資金はどうなりますか
Q 住宅取得等資金の贈与に関して、相続開始前3年以内の贈与について相続財産に加算しなければならないですが、非課税となった住宅取得等資金はどうなりますか
A 相続があった場合、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
※住宅取得等資金の贈与
父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受け、住宅を新築(または取得)したり、増改築等の対価にあてた場合は、一定額までは贈与税が非課
続きを読む >>
住宅取得等資金の贈与に関して、住宅ローンの返済にあてることは?
祖父から1000万円の金銭贈与を受け、住宅ローンの返済にあてようと思います。住宅取得等資金の贈与の特例は使えますか?
この特例は、家屋の新築や取得や増改築の費用などにあてるためのもので、ローンの返済にあてることはできません。
(上記は更新日時点での内容となります。)
※住宅取得等資金の贈与
父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受け、住宅を新築(または取得)したり、増改築等の対価にあて
続きを読む >>
住宅取得等資金の贈与に関して複数の者からの贈与があったときの扱いはどうなりますか?
住宅取得等資金の贈与は贈与者ごとに非課税となるわけではなく、受贈者1人について非課税の枠が定められています。
例えば、年によって変わりますが受贈者1人につき1000万円が上限の年に仮に祖父からの贈与分を非課税枠に充当、父からの贈与分については相続時精算課税制度を選択すると、200万円が住宅取得等資金の非課税枠で使えるほか、残り800万円も相続時精算課税制度の非課税枠(2500万円)をあてるこ
続きを読む >>
解決事例
-
- 2025.09.19
- 想定よりも相続税額を抑えられたケース
-
- 2025.08.27
- 相続財産の中に投資信託が多く含まれるケース
-
- 2025.07.24
- 相続税額をゼロにできたケース