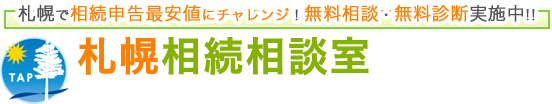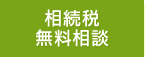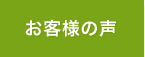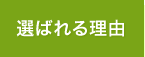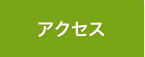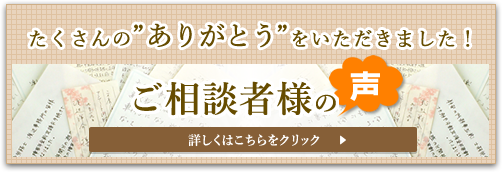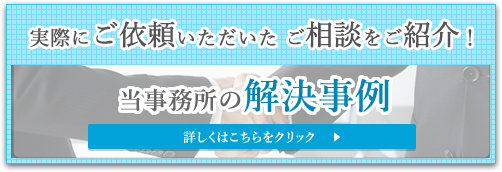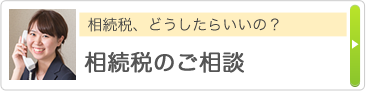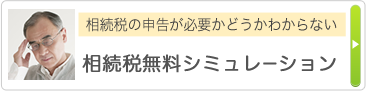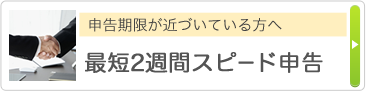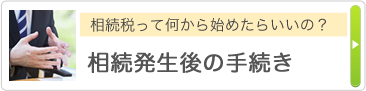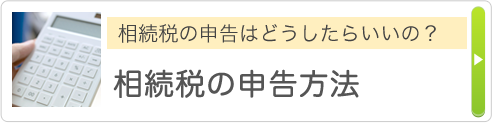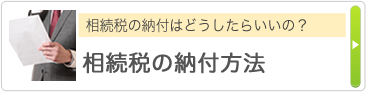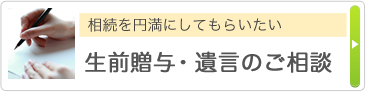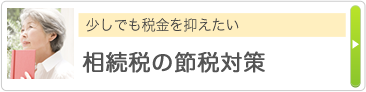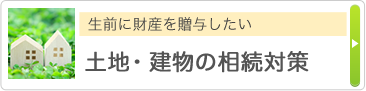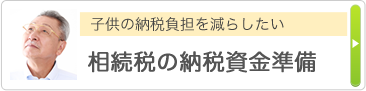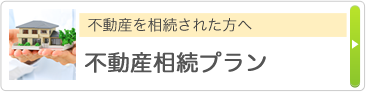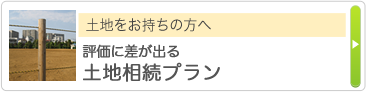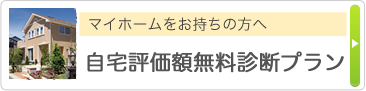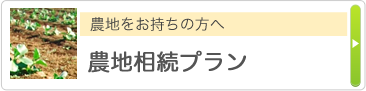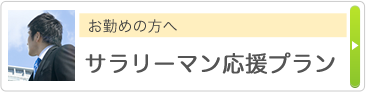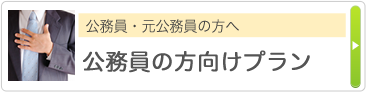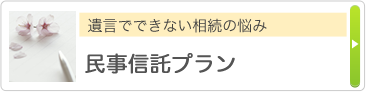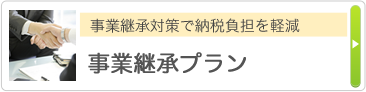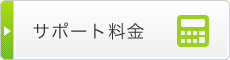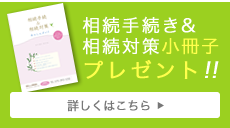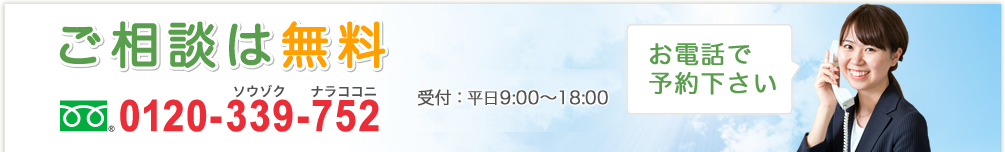残高証明書は相続税申告に必要?必要なケースや発行方法について解説!
身近な方が亡くなられた後、ご遺族には多くの手続きが待ち受けています。その中でも特に複雑で時間のかかる作業の一つが、故人(被相続人)の財産を正確に把握し、相続税の申告や遺産分割を行う「相続手続き」です。
相続財産と聞いて多くの方が思い浮かべるのは、不動産や現金、そして「預貯金」ではないでしょうか。故人がどの金融機関に、どれだけの預貯金を持っていたのかを正確に把握することは、相続手続きの第一歩であり、最も重要な基礎作業となります。
この財産調査の過程で、しばしば耳にするのが「残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)」という書類です。
「残高証明書は、相続税の申告に必ず必要なのだろうか?」
「通帳のコピーやネットバンキングの画面ではダメなのだろうか?」
「どのように取得すれば良いのか、手数料や時間はどれくらいかかる?」
このような疑問をお持ちの方も多いことでしょう。
本記事では、相続手続きにおける残高証明書の役割と重要性、具体的な必要ケース、そして発行手続きの方法や注意点について、プロのライターが詳しく解説していきます。
残高証明書とは何か?
まず、残高証明書とは具体的にどのような書類なのかを確認しましょう。
残高証明書とは、特定の「基準日」時点において、その金融機関(銀行、信用金庫、証券会社、ゆうちょ銀行など)の口座にどれだけの残高があったかを、金融機関が公式に証明する書類のことです。
通常、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人、口座の種類(普通預金、定期預金、当座預金など)、基準日(証明する日)、そして基準日時点の残高といった情報が記載されています。
相続手続きにおいては、この「基準日」を「被相続人が亡くなった日(=相続開始日)」として発行を依頼するのが一般的です。
通帳や残高照会との違い
「故人の通帳が手元にあり、亡くなった日までの記帳も済んでいる」「ネットバンキングで残高を確認できる」という場合、わざわざ手数料を払って残高証明書を取得する必要はないように思えるかもしれません。
しかし、通帳の最後の記帳が亡くなった日と一致しているとは限りませんし、ネットバンキングの画面コピーは、あくまで「その時点で照会した情報」に過ぎず、法的な証明力としては不十分と見なされる場合があります。
その点、残高証明書は金融機関が公式に「相続開始日(亡くなった日)時点の残高」を証明する書類であるため、相続人全員や税務署など、第三者に対する客観的で信頼性の高い証拠となります。
相続税申告に残高証明書は「必須」か?
さて、本題である「相続税申告に残高証明書が必要か」という点についてです。
結論から申し上げますと、残高証明書は、相続税申告書に「添付が義務付けられている書類」ではありません。税務署に申告書を提出する際に、必ず一緒に出さなければならない、という決まりはないのです。
「それなら、取得しなくても良いのでは?」と思うかもしれませんが、そう単純ではありません。税理士をはじめとする多くの専門家は、相続税申告を行うのであれば、残高証明書の取得を強く推奨しています。
なぜ、添付義務がないにもかかわらず、取得が推奨されるのでしょうか。それには、大きく分けて3つの理由があります。
理由1:相続財産(預貯金)を正確に把握するため
相続手続きで最も重要なのは、故人の財産を漏れなく正確に把握することです。
相続人が故人のすべての通帳やキャッシュカードを把握しているとは限りません。近年では、通帳を発行しないネット銀行の利用も増えています。また、故人が家族に知らせず、別の支店に口座を開設している可能性もあります。
残高証明書の発行を依頼する際、「名寄せ(なよせ)」という作業を併せて依頼することで、その金融機関の全支店における故人名義の口座(普通預金、定期預金、投資信託、借入金なども含む)を網羅的に調査することができます。
これにより、相続人が知らなかった口座や金融商品が判明し、財産の申告漏れを防ぐことにつながります。
理由2:相続税の計算を正確に行うため
相続税の計算は、「相続開始日(亡くなった日)」時点の財産価値に基づいて行われます。
預貯金の場合、まさに「亡くなった日の最終残高」が相続財産となります。通帳の記帳が数日前の日付で止まっていたり、亡くなった当日に公共料金の引き落としがあったりする場合、通帳だけでは正確な残高を把握しにくいことがあります。
残高証明書は、この「亡くなった日」時点の残高をピンポイントで証明してくれるため、相続税の課税対象額を正確に算出するために不可欠な資料となります。
理由3:税務調査の対策(エビデンス)として
相続税申告書に添付義務はなくても、申告後に税務署による「税務調査」が行われた場合、申告内容の根拠(エビデンス)として、残高証明書の提示を求められる可能性が非常に高いです。
税務署は、KSK(国税総合管理)システムなどを通じて、金融機関の口座情報をある程度把握していると言われています。申告された預金額が、税務署の把握している情報と大きく異なる場合、調査の対象となる可能性が高まります。
その際、金融機関が発行した客観的な残高証明書があれば、「この証明書に基づいて正確に申告しています」と堂々と主張することができ、申告内容の信頼性を高めることができます。無用な疑いを招かないため、また、調査がスムーズに進むためのお守り(証拠資料)として、非常に重要な役割を果たすのです。
残高証明書が「必要」となる具体的なケース
残高証明書は、相続税申告以外にも、様々な相続の場面で必要となります。
ケース1:相続税の申告が必要な場合
前述の通り、添付義務はなくとも、正確な財産把握、正確な税額計算、税務調査対策の観点から、相続税の申告が必要な(遺産総額が基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える)場合は、事実上、取得は必須と言えるでしょう。
ケース2:遺産分割協議を行う場合
相続税の申告が不要な(遺産総額が基礎控除額以下である)場合でも、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議(誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合うこと)を行う必要があります。
この協議を円満に進めるためにも、残高証明書は非常に有効です。
「故人が亡くなった日に、預貯金がいくらあったのか」という共通の認識を、公式な書類に基づいて全員が持つことで、「もっとあったのではないか」「誰かが隠しているのではないか」といった相続人間の不信感やトラブルを防ぐことができます。
遺産分割協議書に財産目録を添付する際も、残高証明書はその強力な裏付け資料となります。
ケース3:相続放棄や限定承認の手続きをする場合
故人に預貯金(プラスの財産)よりも多額の借金(マイナスの財産)があることが判明した場合、相続人は「相続放棄」や「限定承認」といった手続きを家庭裁判所に申し立てることができます。
これらの手続きを行う際、故人の財産状況を明らかにする「財産目録」の作成・提出が必要となります。その際、預貯金の状況を示す資料として、残高証明書の提出を求められることが一般的です。
ケース4:遺留分侵害額請求を行う(または、行われる)場合
遺言によって「特定の相続人に全財産を相続させる」といった内容が書かれていた場合でも、他の相続人(配偶者、子、直系尊属)には、最低限の取り分を主張できる「遺留分」という権利があります。
この遺留分を計算する基礎となる財産価額を正確に算出するため、また、請求の根拠資料として、残高証明書が必要となります。
残高証明書の発行方法と流れ
残高証明書は、金融機関に依頼すれば誰でも簡単に発行してもらえるわけではありません。相続手続きの一環として請求するには、定められた手順と必要書類があります。
-
誰が請求できるか?
請求できるのは、相続人(法定相続人、遺言による受遺者など)本人、相続人から正式に委任を受けた代理人(弁護士、税理士、司法書士などの専門家、または他の相続人)、または遺言執行者(遺言で指定されている場合)です。
-
どこで請求するか?
故人(被相続人)が口座を持っていた金融機関の窓口です。
基本的には、口座を開設した支店(取引店)でなくても、最寄りの支店で手続きを受け付けてくれることが多いです。ただし、ゆうちょ銀行など金融機関によっては取り扱いが異なる場合があるため、事前に電話などで確認するとスムーズです。
-
いつ(どの時点)の残高を請求するか?
最も重要なポイントです。必ず、基準日を「被相続人が亡くなった日(相続開始日)」として指定してください。
-
請求に必要な書類(一般的な例)
金融機関によって若干異なりますが、おおむね以下の書類が必要となります。不足があると二度手間になってしまうため、事前に請求先の金融機関に確認することをお勧めします。
まず、金融機関所定の「残高証明書発行依頼書」が必要です。これは窓口でもらうか、金融機関のウェブサイトからダウンロードできる場合もあります。
次に、被相続人の死亡が確認できる書類として、除籍謄本(死亡の記載があるもの)や死亡診断書のコピーなどが必要です。
そして、請求者が相続人であることが確認できる書類として、戸籍謄本や除籍謄本など(被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と、請求者自身の戸籍謄本など、被相続人との関係が証明できるもの)が求められます。
(※戸籍謄本を揃えるのが大変な場合、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を取得しておくと、多くの金融機関でこの書類1枚で相続関係を証明でき、非常に便利です。)
さらに、請求者本人の実印と、印鑑証明書(発行後3ヶ月または6ヶ月以内のもの)、請求者本人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)も必要です。
もし手元にあれば、被相続人の通帳やキャッシュカード、証書なども持参するとスムーズでしょう。
代理人が請求する場合は、これらに加えて委任状(相続人本人の実印が押印されたもの)と、代理人の本人確認書類、代理人の印鑑などが必要になります。
-
発行にかかる費用(手数料)
無料ではありません。金融機関ごとに手数料が定められており、1通あたり数百円から1,000円程度が相場です。例えば、三菱UFJ銀行 880円、みずほ銀行 880円、三井住友銀行 880円、ゆうちょ銀行 1,100円などとなっています(手数料は変更される場合があります)。
-
発行にかかる期間
必要書類を提出しても、その場で即日発行されることは稀です。
金融機関内部での確認作業(相続人の確認、口座の特定など)を経て、後日、請求者の自宅へ郵送で届くのが一般的です。
請求から受け取りまで、通常1週間~2週間程度、金融機関や時期(年末年始やゴールデンウィークなど)によってはそれ以上かかる場合もあります。
残高証明書を取得する際の注意点
相続手続きで残高証明書を取得する際には、いくつか知っておくべき重要な注意点があります。
注意点1:口座が凍結される
これが最大の注意点です。
相続人が金融機関の窓口で「残高証明書の発行」を依頼するということは、「口座の名義人が亡くなったこと」を金融機関に公式に通知することを意味します。
金融機関は、名義人の死亡を知った(相続の発生を認知した)時点で、その口座を直ちに「凍結」します。これは、亡くなった方の預金が、一部の相続人によって不正に引き出されるのを防ぐための措置です。
口座が凍結されると、窓口やATMでの預金の引き出しや振り込み、公共料金、クレジットカード、家賃、ローンなどの自動引き落としといったことが一切できなくなります。
(例外的に、相続法改正により一定額(150万円上限)の仮払制度はありますが、原則は凍結されます)
もし、その口座が公共料金などの引き落としに使われている場合、残高証明書を請求する前に、必ず支払い方法の変更(別の口座への切り替えや、振込用紙での支払いに変更など)を済ませておく必要があります。これを怠ると、料金が滞納となってしまうため、十分注意してください。
注意点2:「名寄せ(全店照会)」の依頼を忘れずに
(3章でも触れましたが、非常に重要なので再掲します)
発行を依頼する際、手元にある通帳の支店・口座番号だけを伝えると、その口座の残高証明書しか発行されません。
故人が、同じ金融機関の別の支店に口座を持っていたり、普通預金以外(定期預金、外貨預金、投資信託、国債、出資金など)の金融商品を持っていたりする可能性もあります。
これらをすべて洗い出すために、依頼書の「その他」欄や窓口担当者に、「被相続人名義の全支店・全口座(取引一切)について証明書を発行してください」と明確に依頼(=名寄せ)することが重要です。これにより、相続財産の申告漏れを効果的に防ぐことができます。
注意点3:借入金(債務)も記載される
残高証明書には、預金(プラスの財産)だけでなく、故人がその金融機関から受けていたローン(住宅ローン、カードローンなど)や当座貸越といった借入金(マイナスの財産)も記載されます。
相続は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐのが原則です。負債の正確な把握も、相続手続きにおいては非常に重要です。
注意点4:発行には時間がかかる
前述の通り、発行までには1~2週間以上かかることがあります。また、請求に必要な戸籍謄本一式を収集するのにも時間がかかります。
相続税の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」と定められています。期限に間に合うよう、すべての手続きは余裕を持って、早め早めに進めることを強くお勧めします。
注意点5:外貨預金や投資信託の評価
もし故人が外貨預金や投資信託を持っていた場合、相続税評価額の計算には注意が必要です。
例えば、外貨預金の場合は、相続開始日(亡くなった日)のTTB(対顧客電信買相場)レートで円換算します。投資信託の場合は、相続開始日の基準価額や、解約した場合の手数料などを考慮した価額で評価します。
これらの評価額が残高証明書に記載されているか、あるいは別途「評価証明書」などを取得する必要があるか、金融機関に確認しましょう。
まとめ
残高証明書は、相続税申告書への添付義務こそありませんが、故人の財産を正確に把握し、相続人全員が納得する公平な遺産分割を行い、そして将来の税務調査に備えるために、事実上「不可欠な書類」であると言えます。
たとえ相続税がかからない(基礎控除額以下)ケースであっても、相続人間の無用なトラブルを避けるために、遺産分割協議の資料として取得しておくことが賢明です。
ただし、残高証明書の取得は、口座凍結という重要な注意点を伴います。また、必要書類の収集や金融機関とのやり取りには、想像以上に手間と時間がかかるものです。
もし、相続財産が多岐にわたる場合、相続関係が複雑な場合、または手続きをご自身で行うことに不安を感じる場合は、相続に詳しい税理士や弁護士、司法書士などの専門家に早めに相談することをお勧めします。専門家は、残高証明書の取得代行を含む相続手続き全般をサポートし、皆様の負担を大きく軽減してくれるはずです。
無料相談 / ご依頼の流れ
札幌相続相談室では、相続に関する相談を初回無料にて受付けております。
相談内容に万全を期するため、相談は、お電話ではなく面談でのご相談となります。あらかじめご承下さい。
ご相談の手順
皆さん最初はとても緊張しながらお電話をかけていただいたり、ご訪問されたりしています。
ちょっとしたご質問、ご相談でもかまいません。
まずは無料相談をご利用くださいませ。
以下が、ご相談の手順となります。
1.まずはお電話下さい。
 担当の税理士のスケジュールを確認し、ご相談の日時を調整させていただきます。
担当の税理士のスケジュールを確認し、ご相談の日時を調整させていただきます。
TEL:0120-339-752
【電話受付】平日9:00~18:00
2.専門家による相談
 およそ60分の相談では、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。
およそ60分の相談では、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。
もちろん、相談内容に関しては、法的な見地からしっかりとお答えさせていただきます。
※2回目以降のご相談は11,000円(税込み)/60分となります
3.サポート内容と料金の説明
 相続手続きに関する書類作成から、裁判所に陳述する書類、法務局に提出する申請書類の作成サポートなどは、前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます。
相続手続きに関する書類作成から、裁判所に陳述する書類、法務局に提出する申請書類の作成サポートなどは、前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます。
まずはお気軽にご相談下さい。
TEL:0120-339-752
解決事例
-
- 2026.01.28
- あとから贈与が発覚したケース
-
- 2025.12.19
- 税理士法33条の2(書面添付)を活用したケース
-
- 2025.11.27
- 過去の相続財産が混在するケース